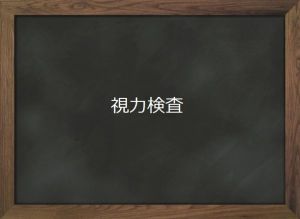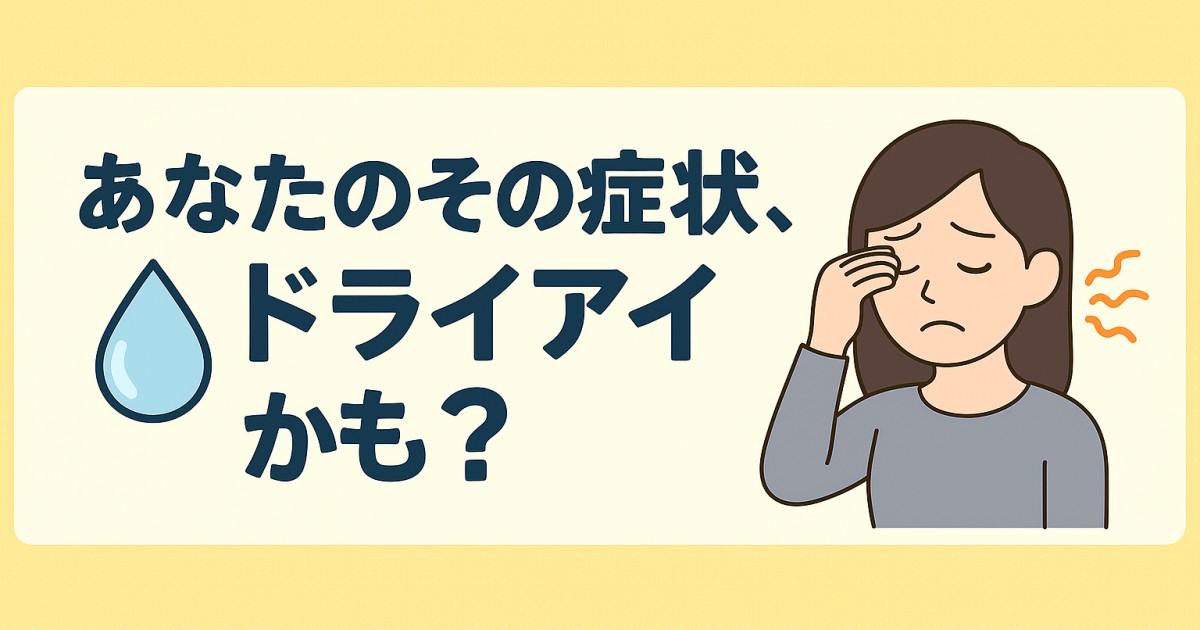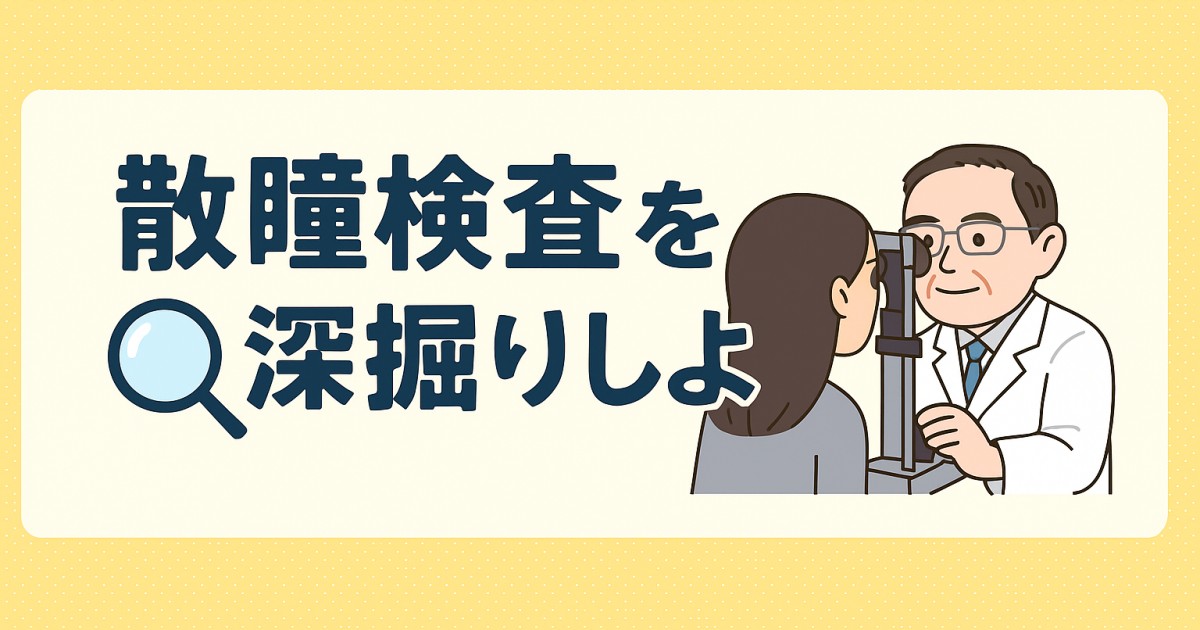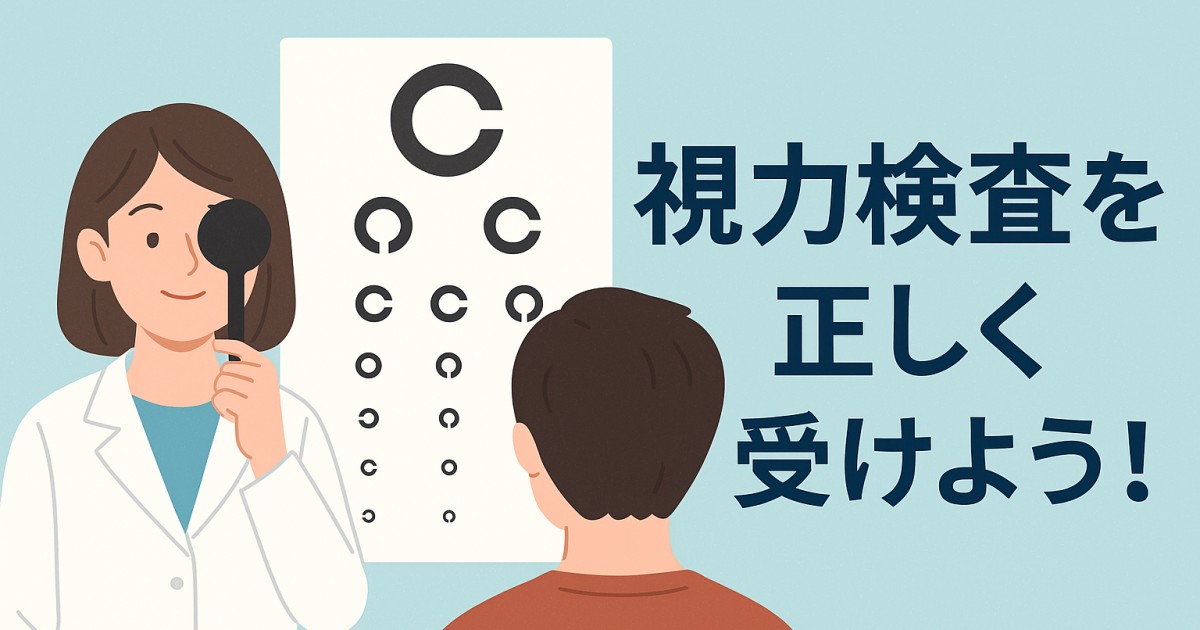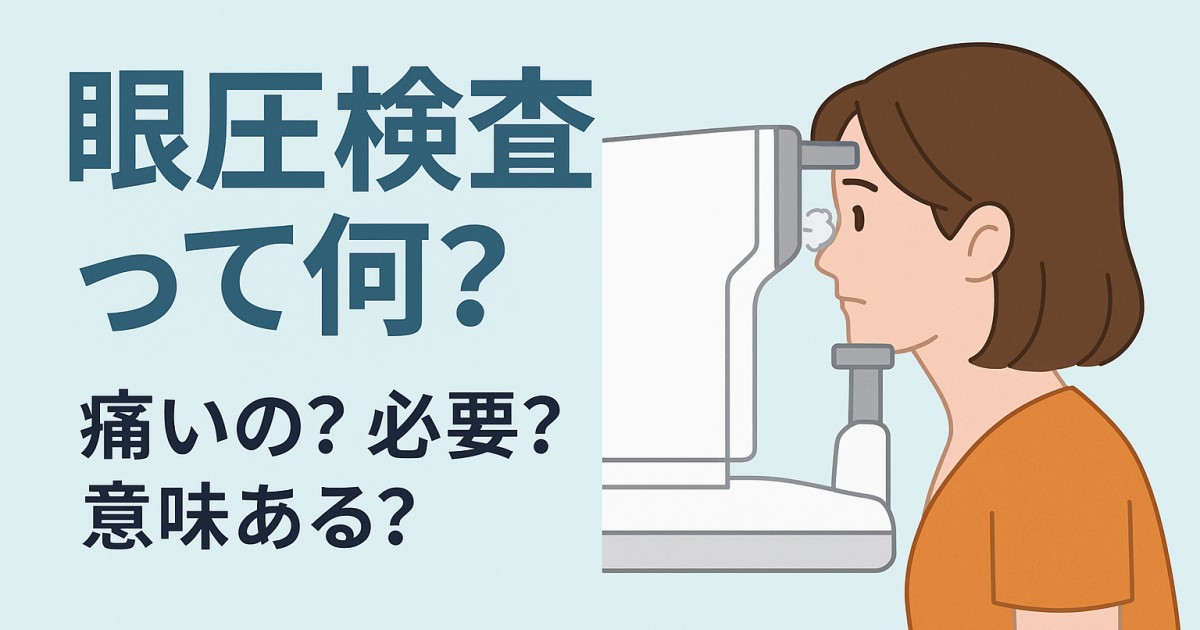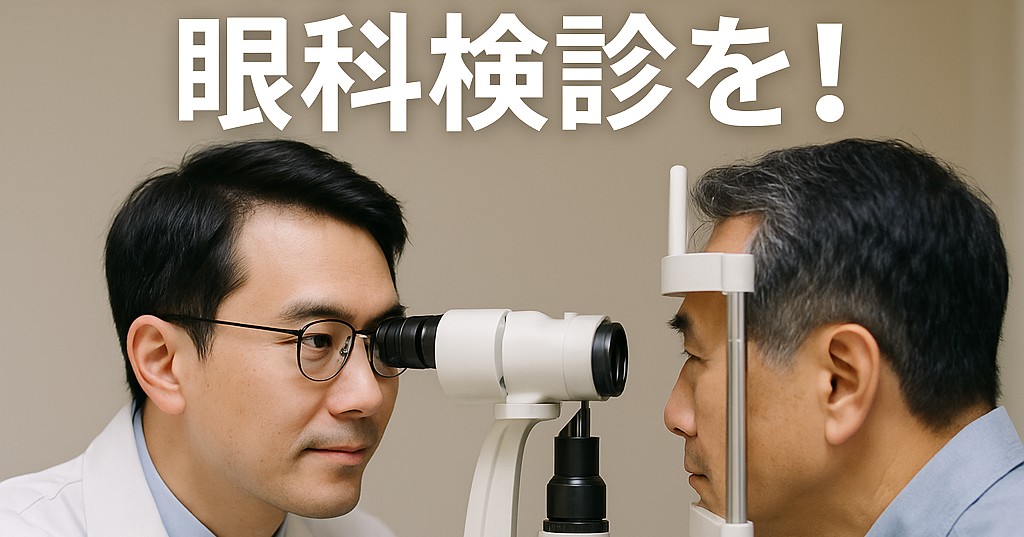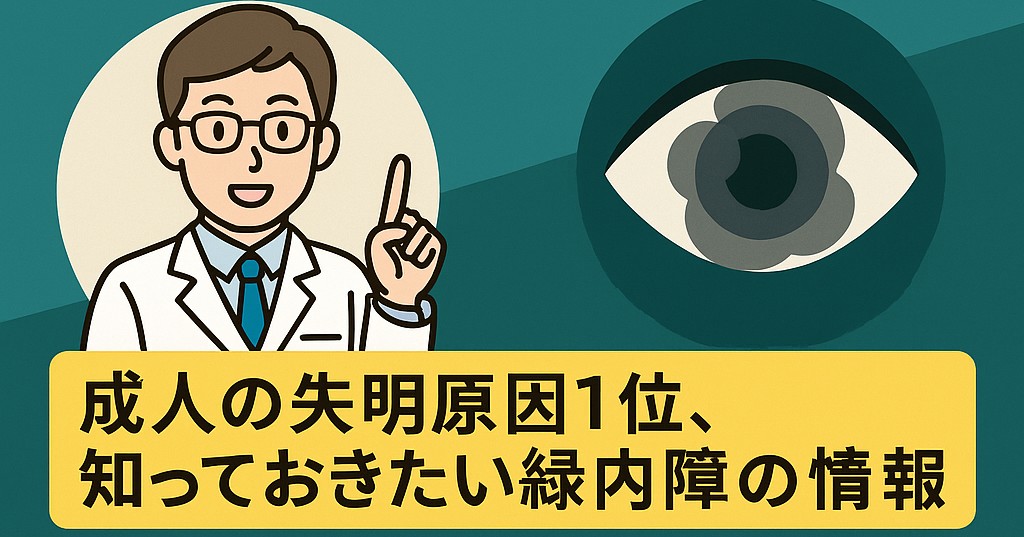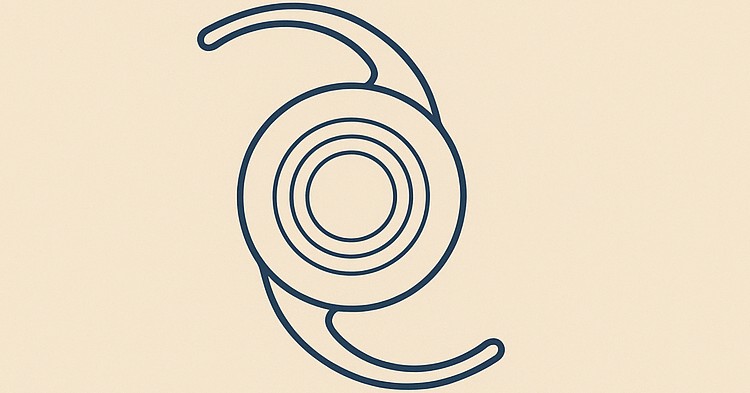今さら聞けない、学校検診の視力検査の意味
毎年のように行われる学校の健康診断の中で、必ず含まれているのが視力検査です。
子どもの頃は「見えるかどうか」を答えるだけの検査でしたが、大人になって振り返ると「なぜ必要なの?」「病院での検査と何が違うの?」と疑問に思う方も少なくありません。
本記事では、学校視力検査の目的や限界、結果の見方について分かりやすく解説します。
学校視力検査の目的
学校で行われる視力検査には、大きく分けて次の4つの目的があります。
-
子どもの視力異常を早期に発見すること
-
学習や日常生活に支障をきたす前に眼科受診につなげること
-
近視・遠視・乱視・弱視といった屈折異常を見つけること
-
すでに眼鏡を使用している場合に、その度数が合っているかを確認すること
視力の異常は子ども自身が自覚しにくく、「見えにくい」と訴える前に進行してしまうケースもあります。学校での視力検査は、そうした異常をいち早く拾い上げる大切な役割を担っています。
学校検診で使われる視力検査の方法
学校で行われる視力検査では、一般的に ランドルト環(Cの形をしたマーク)が使われます。マークの切れ目が上下左右どちらにあるかを答えることで、視力を判定します。
-
検査距離は5mで実施
-
両目ではなく、必ず片目ずつ測定
-
判定は1.0、0.7、0.3といった数値で評価される
学校での検査はあくまで スクリーニング が目的です。大まかに視力の良し悪しを確認することはできますが、正確な屈折度数(近視や乱視の度合い)までは分かりません。また、網膜や視神経といった目の奥の病気を見つけることもできません。
視力検査で分かること・分からないこと
学校での視力検査はとても大切ですが、できることと限界があります。ここを理解しておくと、結果をどう受け止めるべきかが分かりやすくなります。
分かること
-
視力低下の有無:見え方に問題があるかどうかを確認できます。
-
視力の左右差:片目だけ極端に悪い場合も見つけられます。
-
視力矯正の必要性:眼鏡やコンタクトが必要かどうかの目安になります。
分からないこと
-
視力低下の原因:近視、遠視、乱視、弱視のどれなのかまでは分かりません。
-
目の奥の病気の有無:網膜や視神経の異常は分からないため、緑内障や網膜疾患は検出できません。
-
正確な眼鏡の度数:学校検診では眼鏡処方に必要な詳細なデータは得られません。
つまり、学校での視力検査はあくまで、スクリーニング検査です。詳しい診断や治療が必要かどうかは、眼科での精密検査によって初めて分かります。
学校検診で「要再検査」と言われたら
学校の視力検査で「要再検査」と記載された場合は、必ず眼科を受診することが大切です。
学校検診はあくまでスクリーニングであり、そこで異常が疑われた場合には精密な検査が必要です。眼科では視力測定に加えて、屈折検査(近視・遠視・乱視の度合い)、眼底検査、必要に応じて視能検査士による詳細な評価が行われます。
「要再検査」となる背景には次のようなケースがあります。
-
新しく眼鏡が必要なケース:近視や乱視が進行している場合。
-
眼鏡の度数が合っていないケース:眼鏡をかけていても十分な視力が出ていない場合。
-
弱視などの病気が疑われるケース:早期に治療を開始すれば改善が期待できることも多い。
見えにくさを放置すると、学習への集中力低下や姿勢の悪化にもつながります。学校で指摘を受けたら「とりあえず大丈夫だろう」と様子を見るのではなく、早めに専門医を受診することが子どもの将来の視力を守る第一歩です。
まとめ
学校の視力検査は、子どもの目の異常を見逃さないための第一歩です。 しかし、結果はあくまで目安に過ぎません。
-
視力検査は近視・遠視・乱視・弱視などの異常を早期に発見する大切な機会
-
「要再検査」と言われたら、必ず眼科を受診して精密検査を受けることが重要
-
視力は学習や生活に直結するため、早めの対応で改善や進行予防が可能
子どもの見える力を守ることは、学習への集中力や日常生活の質を高めることにつながります。定期的なチェックを行い、将来にわたって健康な視力を育んでいきましょう。
関連記事
すでに登録済みの方は こちら