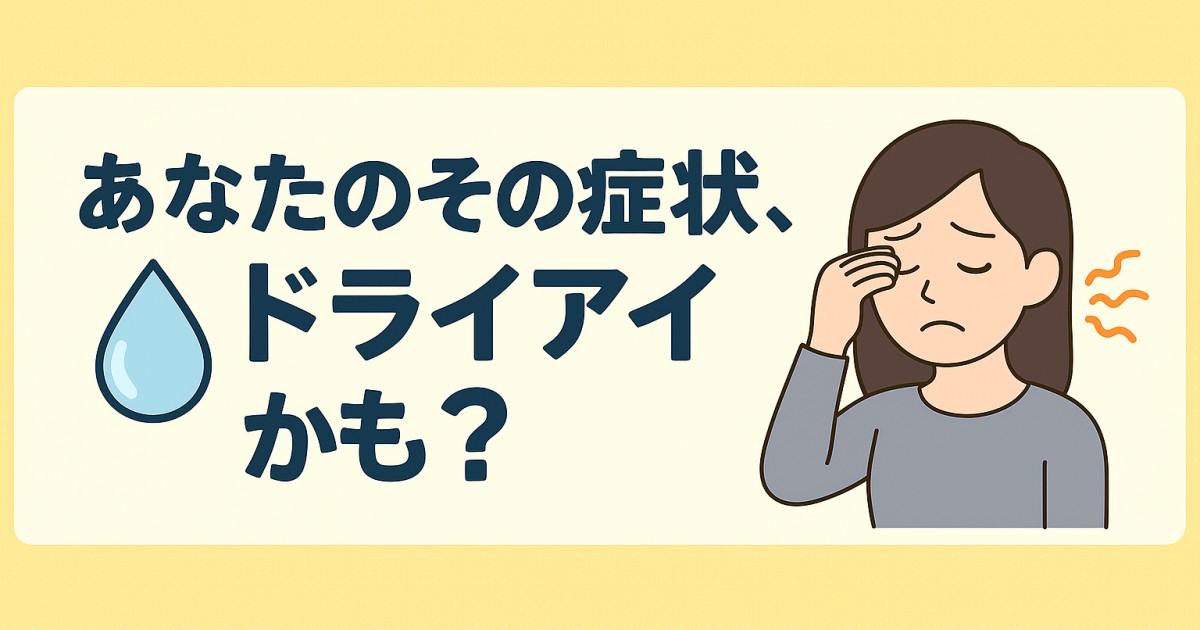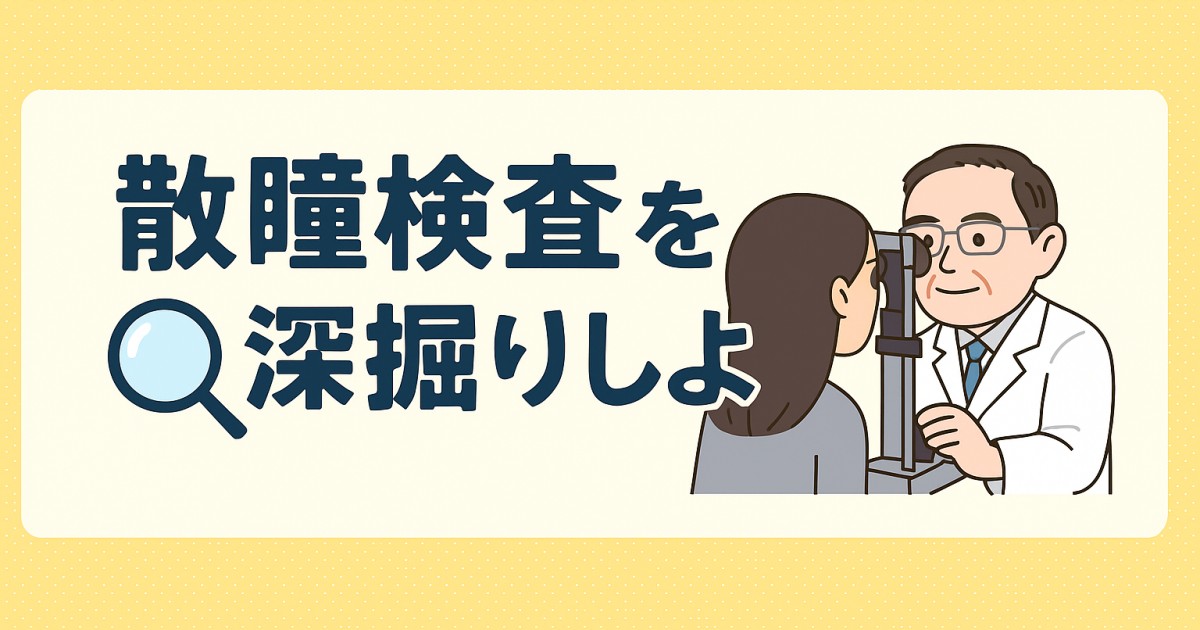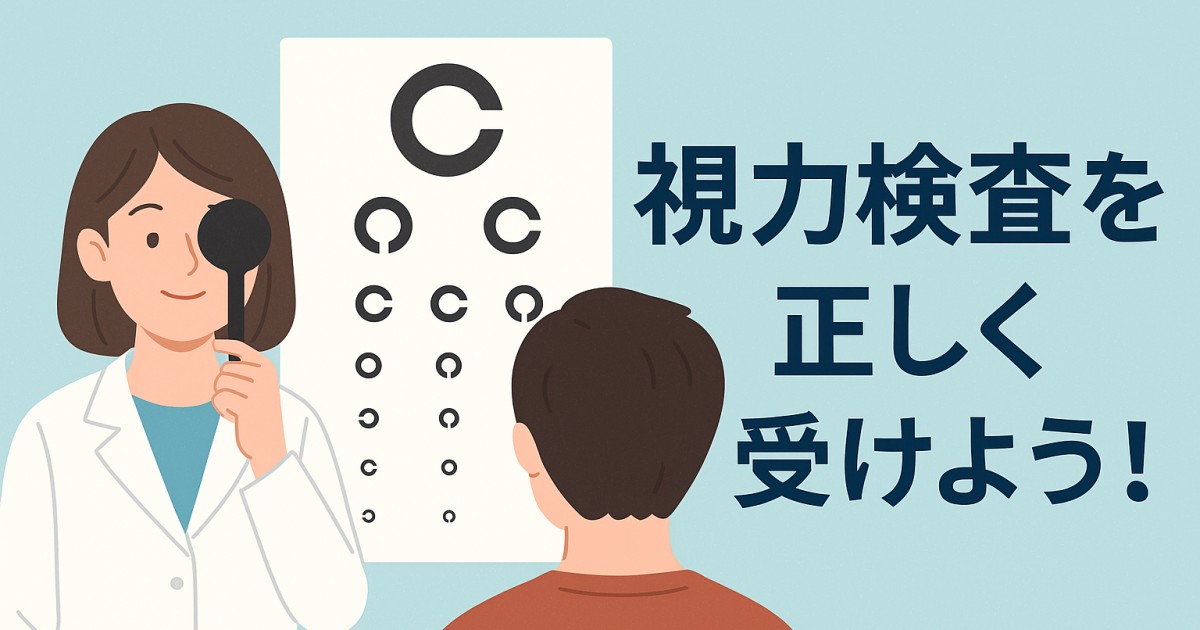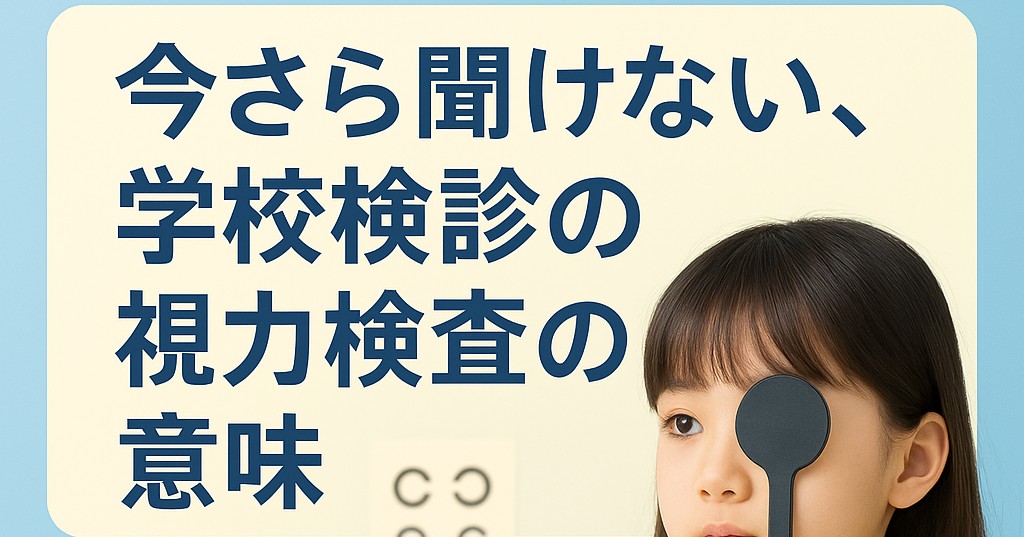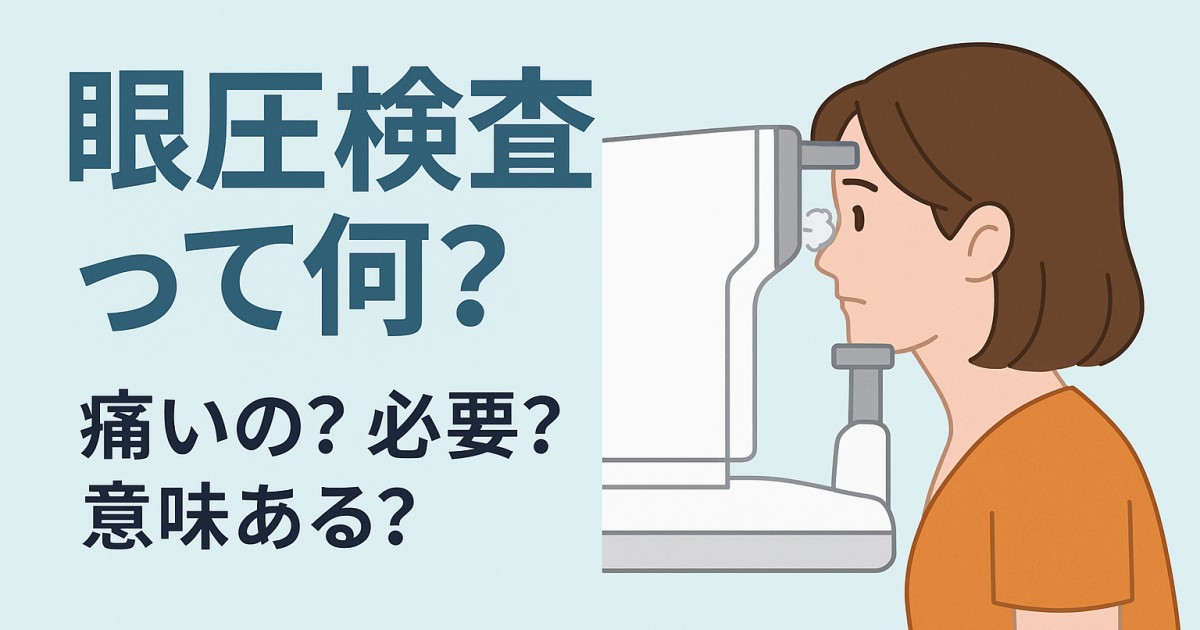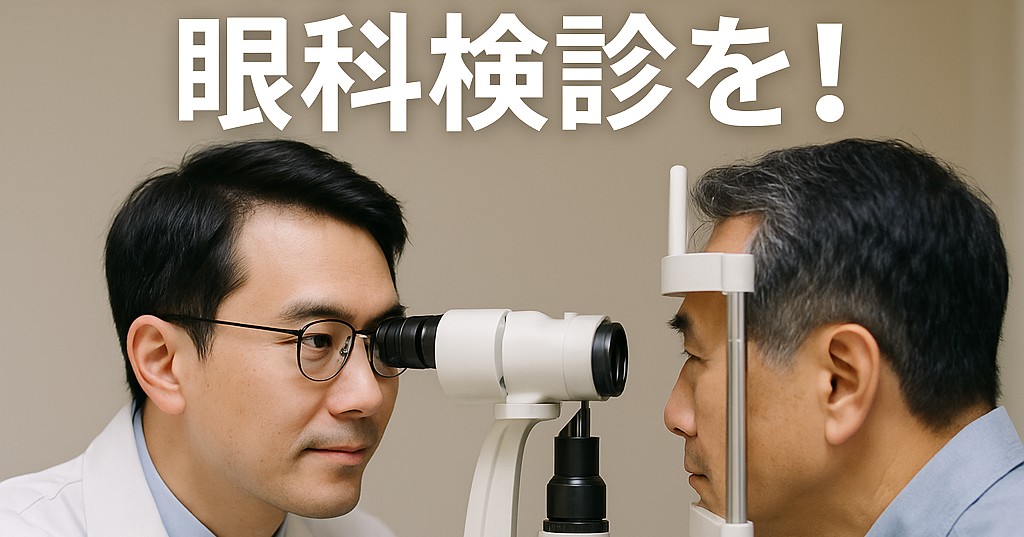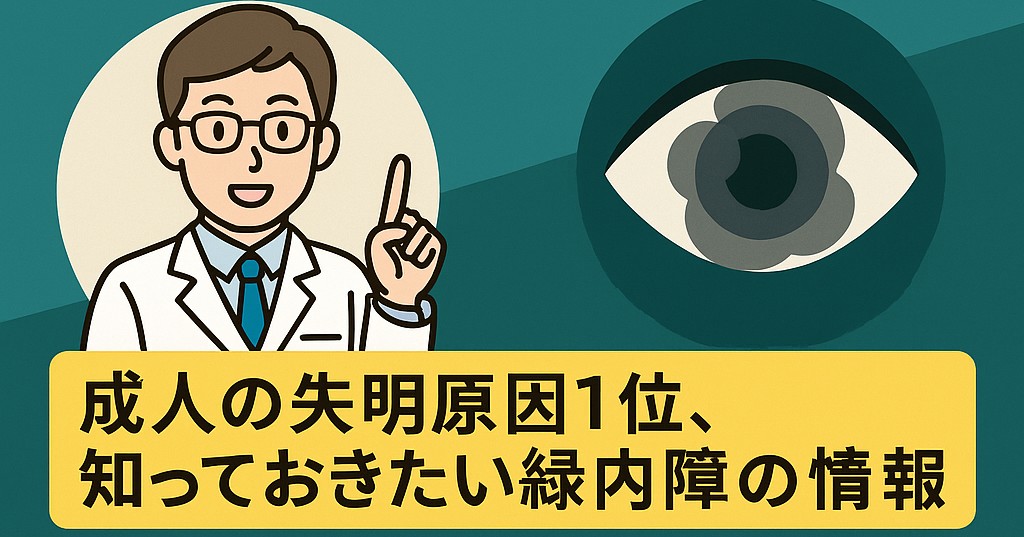本当にいいの?多焦点眼内レンズ
はじめに
白内障手術では、濁ってしまった水晶体を取り除き、その代わりに人工レンズ(眼内レンズ)を挿入します。 近年、この人工レンズの選択肢として「多焦点眼内レンズ」が注目を集めています。
「遠くも近くもメガネなしで見えるらしい」と聞くと、とても魅力的に感じる方も多いでしょう。 しかし、実際にはメリットだけでなくデメリットもあり、すべての人に最適な選択肢というわけではありません。
この記事では、多焦点眼内レンズの特徴や仕組み、メリット・デメリット、向いている人とそうでない人、そして選択時の注意点までわかりやすく解説します。
眼内レンズとは?
眼内レンズ(IOL:Intraocular Lens)は、白内障手術の際に濁った水晶体を取り除いた後、その代わりとして目の中に埋め込む人工のレンズです。 もともと水晶体は、カメラでいうレンズの役割を果たし、光を曲げて網膜にピントを合わせています。白内障ではこの水晶体が濁るため、それを取り除き、人工レンズで代替します。
白内障手術で使われる眼内レンズには、主に次のような種類があります。それぞれの特徴を理解し、自分の生活スタイルや視力の希望に合ったものを選ぶことが大切です。
-
単焦点眼内レンズ:遠く、または近くのどちらか一方にピントを合わせるレンズ。保険適用。 選んだ距離以外はメガネで補正します。
-
多焦点眼内レンズ :遠くと近く、または中間距離も含めた複数の距離にピントを合わせられるレンズ。 メガネの使用頻度を減らせますが、見え方の質に変化が出ることがあります。
-
乱視矯正用眼内レンズ(トーリックIOL) :白内障と同時に強い乱視も矯正できる特殊レンズ。
多焦点眼内レンズとは?
多焦点眼内レンズは、白内障手術で使用される人工レンズの一種で、遠く用と近く用、または中間距離用の焦点を複数持つ特殊な設計になっています。
これにより、従来の単焦点レンズのように「遠くは見えるけど近くはメガネが必要」という状態を減らし、幅広い距離でピントが合うようにすることを目的としています。
種類には以下のようなものがあります。
-
2焦点型:遠くと近くの2カ所にピントが合う
-
3焦点型:遠く・中間・近くの3カ所でピントが合う
-
EDOF(焦点深度拡張型):特定の距離だけでなく、中間から遠方まで比較的広い範囲を連続的に見やすくする
いずれも「メガネに頼らない生活」を目指して作られていますが、焦点を複数に分ける分、見え方の質や光の感じ方が変わることがあります。そのため、特徴をよく理解したうえで選択することが大切です。
多焦点眼内レンズのメリット
多焦点眼内レンズには、生活の質を向上させる可能性があるいくつかの利点があります。特に、メガネをできるだけ使わずに過ごしたい方にとって魅力的な選択肢となると思います。
-
メガネ依存度の低下:遠くと近く、または中間距離も含めて複数の距離にピントを合わせられるため、日常生活でメガネをかける頻度が大幅に減ります。新聞を読む、パソコン作業をする、外を歩くといったさまざまな場面で裸眼で過ごせる可能性があります。
-
生活の自由度向上:旅行や買い物、スポーツなど、アクティブな場面でもメガネの着脱を気にせずに行動できます。特に、アウトドアや趣味活動が多い方にとっては大きなメリットとなるでしょう。
これらの利点により、多焦点眼内レンズはメガネなどがないため、より自然な見え方と快適な日常生活の両方を目指せる選択肢となります。
多焦点眼内レンズのデメリットと注意点
多焦点眼内レンズには魅力的な点も多い一方で、次のような注意点があります。術後の見え方や生活の質に関わる部分なので、事前に十分理解しておくことが大切です。
-
見え方の質の変化:光が複数の焦点に分散するため、単焦点レンズに比べてコントラスト感度(物の輪郭のはっきり感)が低下することがあります。特に細かい文字や暗い場所での作業で差を感じる場合があります。
-
夜間の光のにじみやハロー:街灯や車のヘッドライトがにじんで見える、光の周囲に輪がかかる(ハロー現象)など、夜間視に影響する症状が出ることがあります。夜間運転が多い方は特に注意が必要です。
-
全員に適するわけではない:網膜や視神経に病気がある方、強い乱視のある方は見え方のメリットが得られにくく、適応外となる場合があります。事前の検査で適応の可否を確認することが不可欠です。
-
保険適用外:日本では多くの場合、保険が適用されず自費診療(選定療養)となり、片眼で数十万円かかることもあります。費用面も含めた検討が必要です。
これらの要素は、多焦点眼内レンズを選ぶかどうかの判断に直結します。手術前には必ず医師と十分に相談し、自分の生活スタイルや目の状態に合うかを確認しましょう。