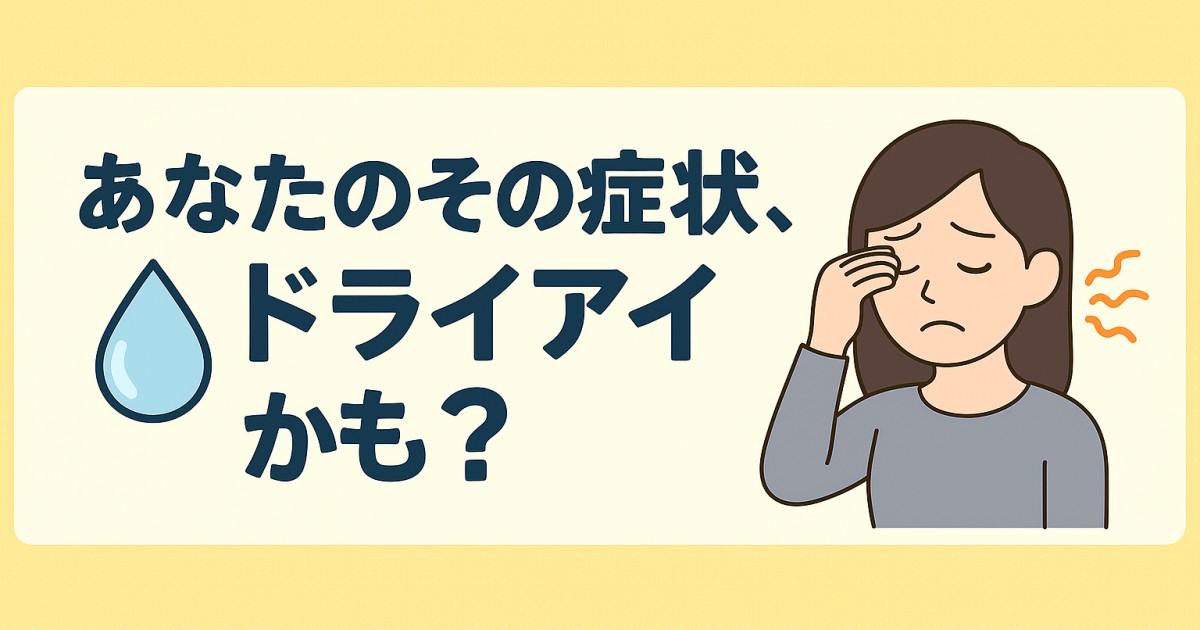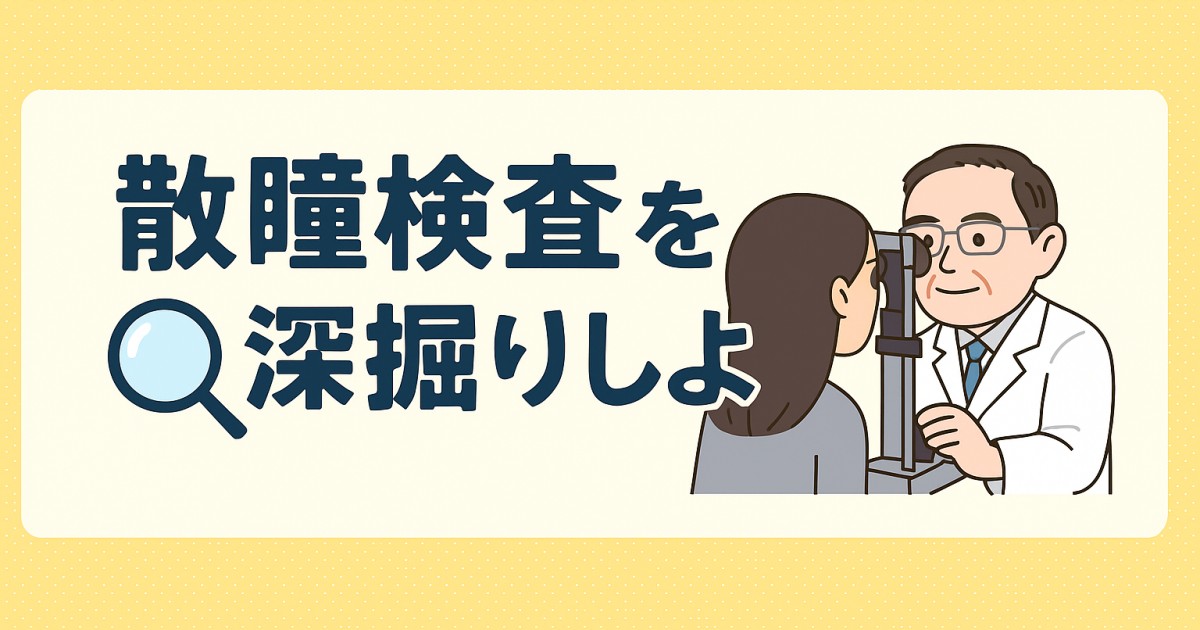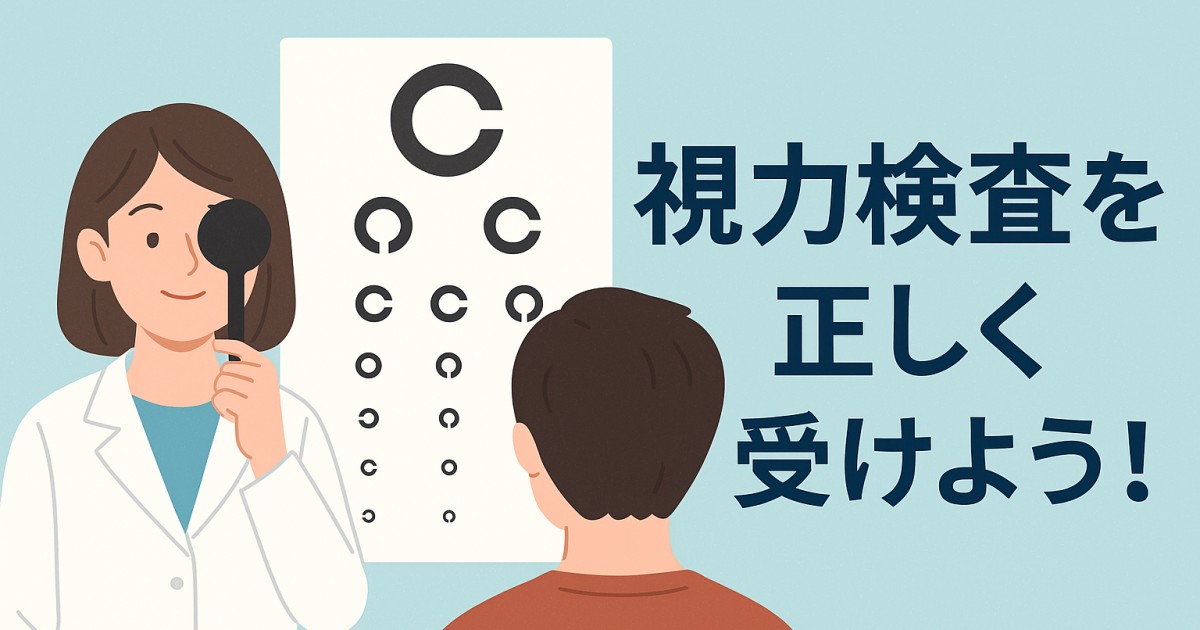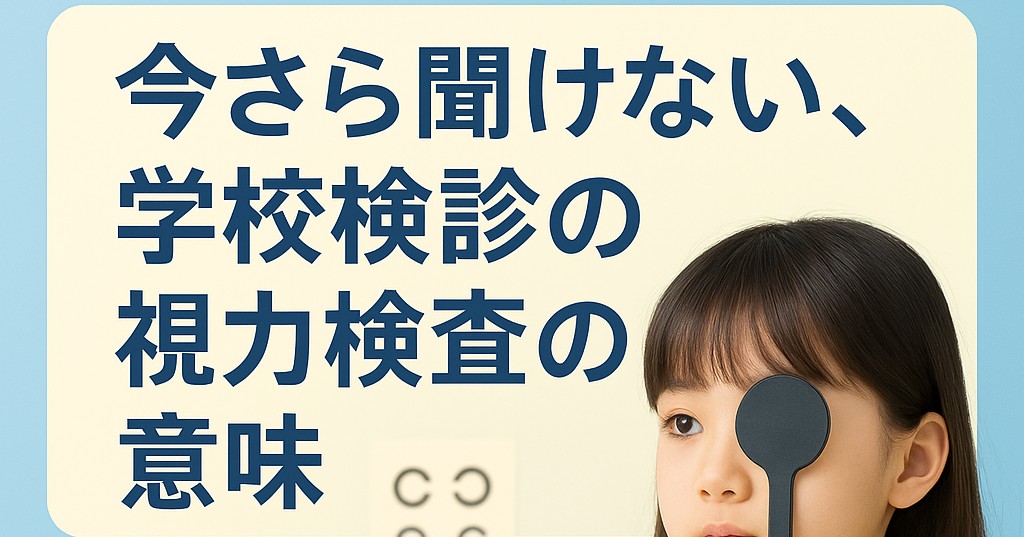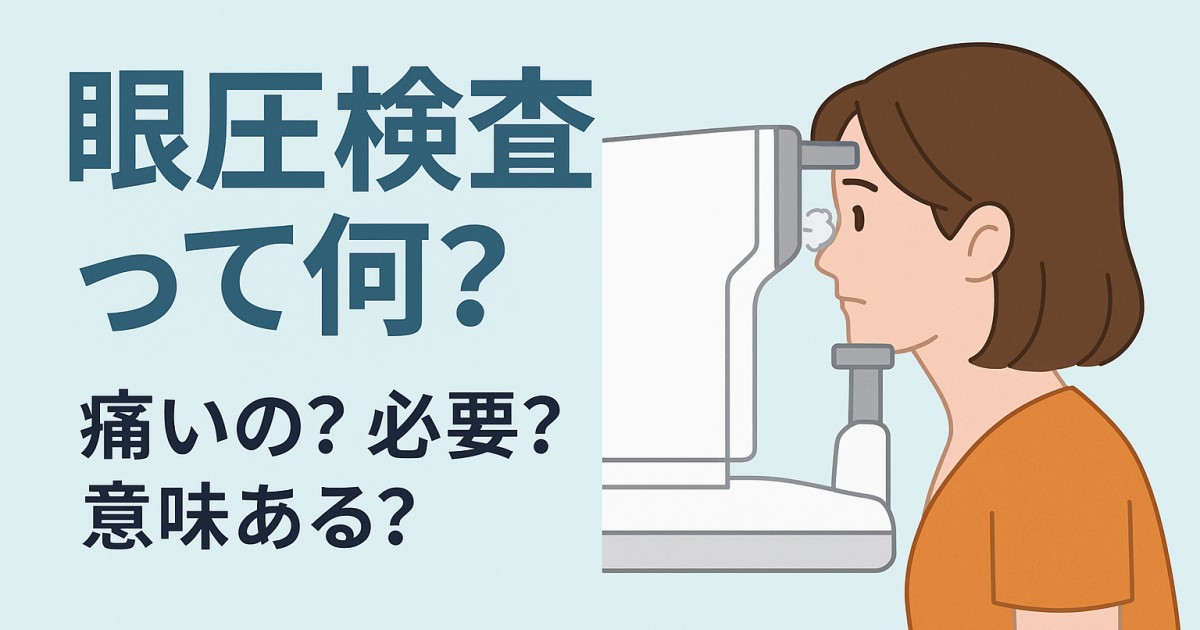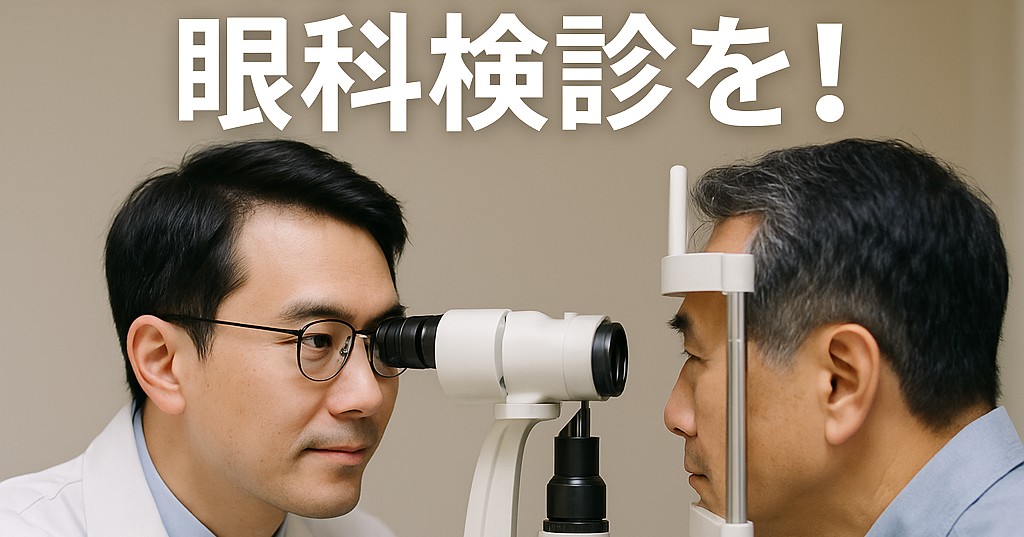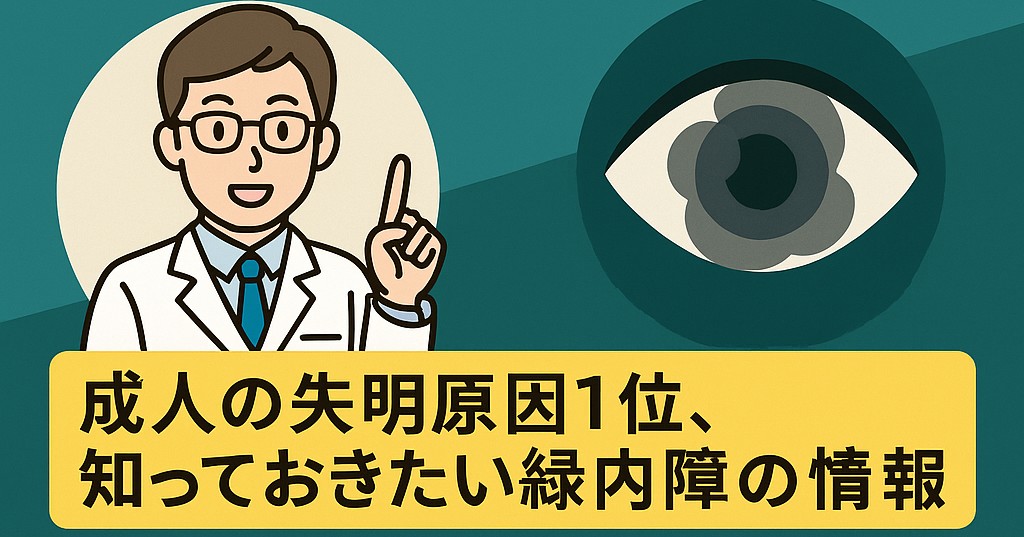そもそも近視ってなに?
近視は「世界的な課題」です
最近「子どもの視力が落ちた」「外で遊ばなくなってから目が悪くなった」そんな声をよく聞きます。実はそれ、近視(きんし)の症状かもしれません。 しかも今、近視は日本だけでなく世界中で急増しています。この記事では「近視とは何か?」という基本から、「どうして増えているのか?」という背景、そしてその予防法まで、最新の疫学情報を交えてご紹介します。
近視とは?
近視とは、遠くがぼやけて見える状態のこと。 目に入った光が網膜よりも手前でピントが合ってしまうため、遠方がぼんやりしてしまいます。近くは見えるので「近視」というわけです。これはカメラのピントが手前にずれているようなイメージです。
近視はどれくらい多いの?
世界の近視人口:爆発的に増加中
-
2000年時点で世界の近視人口は約14億人(全世界人口の23%)。
-
2050年には50億人(約半数)に達すると予測されています【Holden et al., Ophthalmology 2016】。
-
特に東アジアでは深刻で、中国や韓国、日本などの都市部では近視が多いとされています。
日本の状況
-
文部科学省の学校保健統計(令和4年度)によると、裸眼視力1.0未満の割合は小学生で約37%、中学生で58%、高校生では70%以上に達しています。
-
特に都市部や進学校の生徒では、小学生の時点で50%近くが近視というケースも珍しくありません。
なぜこれほど近視が増えているの?
では、なぜ近視が増えているのでしょうか。原因として、両親が近視だと、子どもも近視になりやすいなど遺伝要因もありますが、近年の増加は主に環境要因によると考えられています。
● 目を「近く」に使いすぎている
スマホ、ゲーム、パソコン、読書、こうした近距離作業の時間が長くなると、目のピント調節に負荷がかかり、眼軸(目の奥行き)が伸びてしまいます。これが近視の進行につながります。
● 外遊びの減少
屋外活動の時間が短いことも近視と強い関係があるとされています。 研究では、1日2時間以上の屋外活動をしている子どもは、近視になりにくいことが示されています【Rose et al., Ophthalmology 2008】。
近視の種類と程度
近視にはいくつかのタイプがあります。
-
軽度近視:−3.00D(ジオプター)未満
-
中等度近視:−3.00D〜−6.00D
-
強度近視(高度近視):−6.00D以上
また、子どもの近視は成長とともに進行しやすいため、定期的な視力検査がとても重要です。
近視が進むとどうなる?
軽い近視ならメガネやコンタクトで補正すれば問題ありません。しかし、近視が進むほど下記のような目の病気になるリスクが増します。
-
網膜剥離(もうまくはくり)
-
緑内障(りょくないしょう)
-
近視性黄斑症(きんしせいおうはんしょう)
これらは失明につながる病気のリスクを高めるため、近視にならない、進行を抑えることが重要となります。
どうすれば近視を防げる?
完全に防ぐことは難しいですが、進行を遅らせると期待されている方法はいくつかあります。
● 外で遊ぶ時間を増やす
自然光の中で過ごすことで、近視の進行が抑えられると言われています。 目安は1日2時間以上の屋外活動です。いきなり2時間を確保するのは難しいですから、学校の休憩時間などを考慮に入れて、少しずつ屋外活動を取り入れていきましょう。
● 近くを見続けない
スマホ・ゲーム・読書は30分に1回、目を休めることを意識しましょう。 20-20-20ルールもおすすめです。20分に1回、20フィート(約6m)先を20秒見ることで、子どもの場合は近視の抑制に、大人の場合は眼精疲労(目の疲れ)に有効なことがあります。
● 定期的な眼科受診
特にお子さんの場合、見えづらさを自分でうまく伝えられないことがあります。学校検診で指摘がなくても、見えにくそうにしていれば、年に1回の眼科受診できると安心です。
まとめ:未来の目を守るのは、今日の習慣
近視はすぐに危険な病気というわけではありませんが、進行すると失明につながる病気のリスクが高まります。 特にお子さんの場合、「目が悪くなるのは仕方ない」とあきらめず、今できる予防策をコツコツと積み重ねることが大切です。将来も健康な視力を保つために、今日から少しだけ意識してみませんか?
すでに登録済みの方は こちら